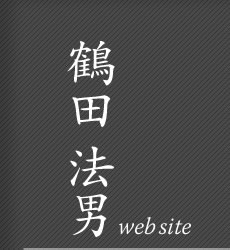映画、テレビ、ちょっぴりビデオの時代があって、そしてネット。時代は確実に変わっている。
自分も映像業界で働いているのでちょっと書きづらいところがあるのですけど、先日、某スポーツ紙の記事で、某役者さんがテレビや雑誌に「過剰露出」したので某映画がかえって不入りになった、という個人的にはなんともいやらしく感じる記事を読みました。
でも、この「過剰露出」というのが我が家ではピンとこない。
実は、毎日勉強に追われている中学生の娘が可哀想なので我が家のリビングのテレビで見る番組は娘の意向を尊重しているのですが、娘が見たがるのはHIKAKINなどのユーチューバーの動画なのです。
最近のテレビモニターやビデオレコーダーは良く出来ていて、テレビなのにネットが手軽に見られるようになっているからそうなってしまいました。で、本来のテレビ番組は本当に見たいものだけをオンエアで見るか、タイムシフト視聴が日常です。娘の友達が遊びに来てもやっぱりユーチューバーやボカロのミュージックビデオを見てますね。
テレビや雑誌に多数登場するのが「過剰露出」と思っているのはある年齢層から上だけで、そもそもこの某スポーツ紙の記事が時代とズレてるような気がしました。
そういえば、昨年のヒットドラマ『逃げ恥』はネットを有効活用したのが功を奏したとも聞いています。
私の祖父は勝新太郎、市川雷蔵などのスターを抱え、『ガメラ』、『座頭市』、『眠狂四郎』などの人気シリーズや、黒澤明監督『羅生門』などを製作した大映という映画会社の役員でした。しかし、60年代に普及したテレビに押されて1971年に倒産しました。私は子供ながらその瞬間を見ています。
また80年代、ビデオソフト発売会社に大学卒業後に就職した私はビデオレンタル店の影響で各地の映画館が閉館に追い込まれるのを目の当たりにしました。私の父が経営していた名画座・三鷹オスカーは特異なプログラムで生き残り、1990年に閉館をした理由も「三鷹市の駅前再開発事業」の区域に入っていたからでした。でも、閉館までの間、ビデオ産業発展の影響が経営に無かったかというと嘘になります。
そして今は、ネットがテレビよりも大きな力を持ち始めていて、時代は確実に変わりつつある。
ところが、それを受け止めず旧態依然とした発想でしか仕事をしないテレビ関係者が居らっしゃる。
既存メディアの立ち位置を根本的に捉え直さないといけないし、諸々のエンタメや芸能関係のプロモーション戦略も考え直さないといけないはずです。
以上のような事から、テレビは危機感を持たないといけないはずなんです。
それを以前あるテレビ人に語ったら「やる気が無い」とか「勉強不足」とか逆ギレされてしまいました。
とても残念な気持ちになりましたので、ここにひっそりと記しておきます。